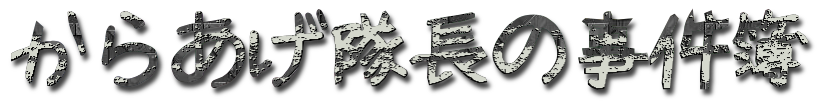こんにちは。からあげです。
はじめに
初めての自転車の組み立てはまだ始まったばかり。
前回はリムのバルブ穴拡張とタイヤ・チューブの装着まで。今回はフレームのネジ穴の修正を行う。

序盤で問題発生!
届いた荷物の確認で見つかったネジ穴の不具合。その問題のネジ穴はフォークにあるブレーキ (フラットマウント)のもの。
2個あるうちの下(先の方)の方はネジ山がほとんどない。

フラットマウント上側のネジ穴
不鮮明ではあるがまだネジ山はある。若干の違和感はあるものの、手でネジを締め込むことができる。

フラットマウント下側のネジ穴
ほとんどネジ山なし、ネジを入れようにも硬くて全く入らない。
当たり面の処理も見るからに悪い。
このままでは組み立てられない。非常に残念だが、これも勉強の機会だと前向きに捉えて作業を進めることにした。
ツーリング車のブレーキはフラットマウントよりもインターナショナルスタンダード

モトクロスインターナショナルのウェブサイト(http://ride2rock.jp/products/115098/)より借用
話は変わるが、サーリーは未だに多くの車種でのブレーキマウントにインターナショナルスタンダード(以後ISとする)を用いている。その理由は信頼性が高いからだと思われる。
それを証拠にツーリング車の新型ディスクトラッカーはフラットマウント仕様になっているが、フォークのマウントにはリヤ用アダプターで取り付ける特殊な仕様になっている。つまりフォークも貫通穴でネジ山はなし。
旧式のISはアダプターを使ってポストマウントのブレーキキャリパーを取り付ける。
ちなみにフラットマウントは、アダプターを使えばポストマウントのブレーキキャリパーを装着できるが、ISやポストマウントにはフラットマウント用のブレーキキャリパーは装着できない。上位互換性があるのみ。買い換えろという無言の圧力を感じる。笑
IS仕様のフレームにはネジの貫通穴のみでネジ山はアダプターの方にある。そのためネジ山を傷めたとしても、アダプターを交換するだけで簡単に復旧できる。海外の僻地を走る長期ツーリングには、旧式のISマウントの方が断然良いだろう。
私の旧型ディスクトラッカーはISマウントだが、日常生活やツーリングでも全く問題ないし、愛着が湧いているので新型に買い換える予定は全くなし。似たような自転車よりも、新たなジャンルの自転車が欲しいと強く思う。笑
安価だがちゃんと使えるタップ・ダイスセット

今回のネジ山の修復はもっとも簡単なタップを使う方法で行う。タップでネジ山を切って修復できるなら、あえて難しい方法を取ることはない。
ちなみにタップ以外にヘリサート加工というのもある。元のネジ穴より大きめの下穴を空けてタップでネジ山を切り、そこにコイルを埋め込む修理法。メリットはヘリサートで修復したネジ穴は元の穴より丈夫になること。
ほかには元よりネジ穴を少し大きく広げるか、信頼できる自転車屋さんにお願いして、溶接で穴を塞いで再度空け直す、などがある。安全に非常に関わるブレーキなのでプロに任せた方が無難だろう。
今回購入したのはイーバリューのタップ・ダイスセット。必要なサイズを単品で購入するよりもセットの方が安くなる。
お手頃価格でAmazonでの評判もそこそこ良い。中にはこき下ろす人もいるが、たぶん使い方が悪い。使用頻度が少ない一般人はこれで十分ではなかろうか。高価な道具を揃えても腕が悪かったら意味無し。
今後のためにピッチゲージが付く豪華40pcsを選択した。



セット内容:タップハンドル・ダイスハンドル・T型タップホルダー・ピッチゲージ・精密ドライバー・収納ケース
ダイスサイズ:3×0.5・3×0.6・4×0.7・4×0.75・5×0.8・5×0.9・6×0.75・6×1.0・7×0.75・7×1.0・8×1.0・8×1.25・10×1.25・10×1.5・12×1.75・1/8-BSP
タップサイズ:3×0.5・3×0.6・4×0.7・4×0.75・5×0.8・5×0.9・6×0.75・6×1.0・7×0.75・7×1.0・8×1.0・8×1.25・10×1.25・10×1.5・12×1.5・12×1.75・1/8×BSP
材質:タングステン鋼

ブレーキキャリパーの取り付けビスはM5サイズ。
ピッチゲージでビスのピッチを計測しておく。

0.9mmを当てると隙間ができる。

0.8mmを当てるとピタリと嵌まる。つまりピッチは0.8mmということ。
修正作業のようす

フォークはバイス(万力)に挟んで固定したいところだが、作業台に置いた方が作業しやすかったので固定せずにやることにした。
タップを使ったネジ山の修復作業は今回が初めて。あわてず慎重に行う。
切削油は安いチェーンオイルを使った。
タップを取り付けるハンドルは通常タイプとT型ホルダーの2種類ある。

まずはT型ホルダーで試してみた。
だがハンドルが動くうえに結構なガタがあって危険な感じがする。ここは本能に従ってすぐに作業を中断した。

通常のタップハンドルを試してみる。
今度はガタはなくなったが、ハンドルが重たく少しでもブレると、タップの刃先が結構ブレる。力加減も難しい。小型のハンドルも欲しいところ。

試行錯誤しているうち、まず初めはハンドルを付けずにタップだけを手で回した方が良いことが分かった。
その方がズレたままの状態でネジ山を切ってしまうおそれが少ない。

ある程度入っていったら、一度抜いてハンドルを付けて回す。
一度にネジを切ろうとはせずに、1,2回転回しては戻して切削油を垂らし、再度1,2回転回すを繰り返す。常に垂直を意識して作業を進める。

作業している場所は北西の季節風がまともに当たるオープンスペースで凄く寒い。強い風が吹くとビスなどの小さな部品は飛ばされそうになる。
しかも物置の出入り口の前で家族が通る。母が無駄に行き来して集中できない。繊細な作業中に何度も横切られると非常に煩わしい。作業に没頭するには、ある程度整った作業環境が欲しいところだ。

削りカスはこまめに取り除いて切削油を垂らす。
ハンドル側は小さなブレでも刃先は大きくブレる。ネジ山の修復は本当に繊細な作業だ。
タップがブレるとネジ穴が大きくなってしまい、キャリパーをしっかりと固定できなくなる。

修復したネジ山。ホッと胸を撫で下ろす。

ビスを入れてみるとスムーズに回せる。若干のガタはあるが、これでヨシ。
やり過ぎるとネジ穴がガバガバになって使い物にならなくなる。
人間ときには妥協が必要だ。笑

もう一つのネジ山も修正してスムーズにビスを回せるようにした。これでヨシ。
おわりに

こうして初めてのタップによるネジ穴修復は無事終わる。
自転車屋さんで組んで貰っていると、こうした眼に見えない作業には気づかない。素のフレームから組んでゆくのは面倒だが、悩ましくもあり楽しくもある。こんな楽しいこと人に任せては勿体ない。
こうして試行錯誤しながら地道に経験を積んでいけば、ホイールも自分で組めるようになるだろう。めでたく無事に修復作業が終わってなにより。度々ものを壊す癖のあるおっさんだが、今回はちゃんとできた。